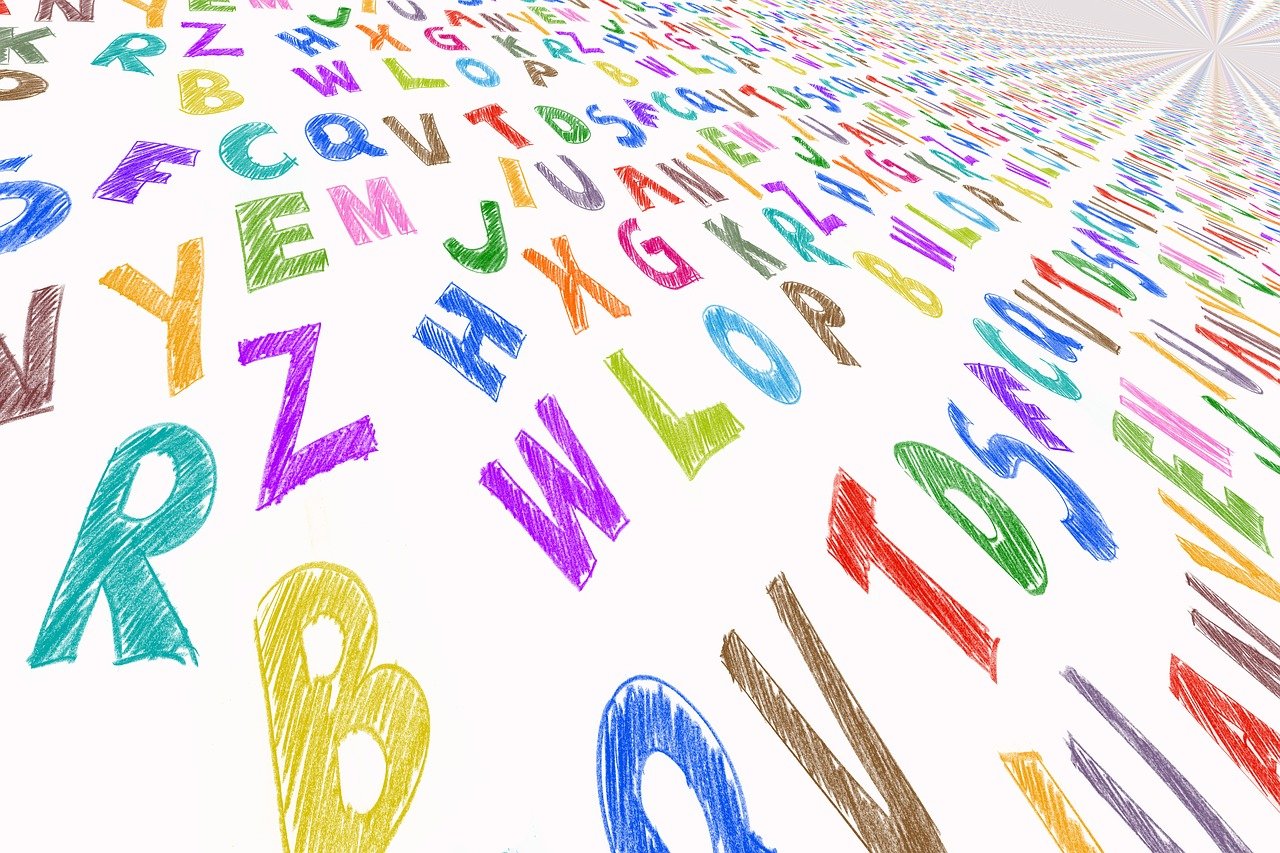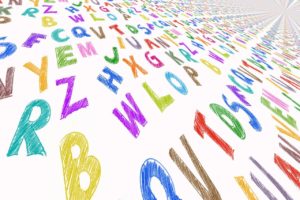マレーシアで大学生活を送っていると、英語も日本語もある程度話せるけれど、どちらも中途半端という日本人学生をよく見かけます。
こうした状態はダブルリミテッド(Double Limited)問題と呼ばれ、二つの言語を扱えるように見えて、実際にはどちらの言語でも深い思考や表現が難しくなる現象です。
私自身、海外で暮らす中でこの問題に直面している日本人(主にインター卒)を何度も目にしてきました。
今回は、「英語ができる=良い教育」と思われがちな今の時代だからこそ、言語の量ではなく、思考の深さを支える軸を持つことの重要性を感じます、という話をします。

言語そのものは目的ではなく、コミュニケーションツール
思考力こそが本質
多くの人は、言語を「話すための目的」だと考えます。
けれど実際には、言語は思考を支えるツールに他なりません。私たちは、頭の中で言語を使って考えます。
文章を読んで内容を理解したり、物事の因果関係を整理したりできるのは、その言語の中にある概念を使って論理を構築しているからです。
もしその言語の理解が浅ければ、思考の深さも浅くなります。
会話はできても、複雑な内容を説明したり、議論の筋を通したりするのが難しくなる。これは単なる語学力の問題ではなく、どの言語で思考を鍛えてきたかという根本的な問題です。
そのため、大事なのは言語の発音や語彙力がどうといった問題ではなく、根本的な思考力があるかどうかなのです。
「英語ができる=良い教育」ではない
近年はインター校やバイリンガル教育が人気で、「英語が話せる=優秀」と捉えられがちです。
しかし、英語はあくまで目的を果たすための手段でしかありません。ほとんどの人が言語を学ぶ動機は、人と話したい、仕事で必要、海外で暮らしたい、といったつながりのためです。そちらが本質。
ネイティブのような発音や完璧な文法が必須というわけではありません。むしろ大事なのは、筋の通った内容を話せること。
例えば、YouTubeではひろゆきが海外で英語で詐欺師と格闘している動画などがありますが、発音が完璧なわけではないのに内容が伝わる。
それは、話の構成が論理的で、言葉の裏に思考があるからです。だから、言っている内容が相手にも理解される。
逆に、マレーシアで英語の発音はやたらと良いけれど英語が伝わらない日本人を見てみると、大体は日本語で話を聞いても話がわかりづらいので、英語力とかの問題ではないのだと思います。
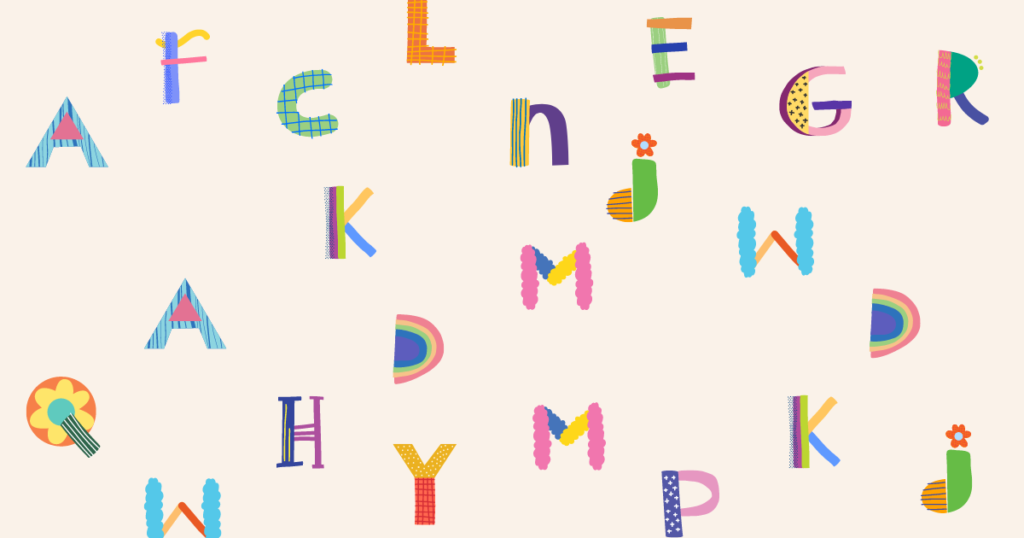
思考力は大人になってからでは鍛えにくい
大人になると伸ばしづらいもの
大人になってからでも、発音や語彙のような表層的な言語スキルは伸ばせます。しかし、論理的思考力や抽象的な理解力は、母語を通して鍛えられるものです。
本を読み、要約し、意見を述べる、そうした積み重ねの中で、物事を構造的に捉える力が育ちます。
それが十分に形成されないまま成長すると、どの言語を使っても思考が散らかってしまう。だからこそ、子どものうちに1つの言語で深く考える経験を積ませることが何より重要だと思います。
両方を少しずつより、ひとつを確実にする方が強い
私は、英語も日本語も「そこそこ」できる状態よりも、母語でしっかり考えられる力を育てる方が価値があると考えています。
つまり、どちらの言語も7, 8割ずつよりは、どちらかの言語が弱くても良いから一つの言語で思考を完結させられる状態をまず作ること。
その上で、もう一つの言語を「伝えるための橋」として身につければいい。
完璧な英語よりも、自分の考えを自分の言葉で整理できる力の方がずっと強い。思考の深さは、語彙力よりもずっと再現が難しいのです。
結論:母語の地盤がある人は強い
結局、子どもにとって一番大切なのは「英語が話せること」ではなく、自分の言葉で考えられることだと思います。
その力があれば、英語はあとからでも学べるし、発音が多少違っても伝わる。
言語は単なるスキルではなく、思考を育てる土台です。そして、その土台がしっかりしている人こそ、どの国でも強いと思います。