文章が上手に書けるようになるとマジで人生が好転します。
急にこんなことを言うと「何コイツ、ウザ」って思われるかもしれないんですが、私の文章はよく「分かりやすい」と褒めていただけることが多いです。
- 高校時代には論文などの執筆経験多数
- 科学研究コンテスト全国一位や全国入賞の経験あり
- 東京大学の推薦入試の書類審査通過
- 英語のエッセーコンテスト受賞、その他
- 海外大学の平均点70点以下のエッセー課題で90点以上を獲得
- 教授からも「文章の構成が素晴らしい」と評価
- 本職の留学エージェントからこの留学ブログの品質を絶賛されたりも
- 文章だけでなく、プレゼンや面接も超得意
そんなことがあって、なんと現在はライターとして仕事をいただけたりもするようになりました!
というわけで、今回はそんな私が僭越ながら「分かりやすい文章」を書くコツと、その練習方法を伝授します!
脳内を全部言語化したので記事書くのにメッチャ時間かかったんですが、その分内容には自信があります。
これを見れば今日この瞬間から、文章作成、プレゼン、面接が圧倒的に上手くなります。長くなりましたが最後まで読んでくださいお願いします。
注意:ここではストーリーライティングや小説のテクニックは扱いません。あくまで論理的な説明文に焦点を当てます。

文章が上手になると人生が変わる
論理的な文章を書けるようになると、こんなメリットがあります:
- 人に話を理解してもらいやすくなる:
文章力が上がれば、面接での説明も自然と上手くなります。論理的な伝え方は会話にも応用可能。 - 信頼が得られる:
明確で筋の通った文章を書けるとしごでき感が出ますし、読み手にも信頼感を与えられます。 - 仕事がもらえる:
分かりやすい文章はビジネスシーンで重宝され、ライティングの仕事やプレゼンの機会が増えます。ライターにもなれる! - ここぞ!という場面で成果を出せる:
受験やコンテスト、プレゼンなど、重要な場面で説得力のある文章が書ければ、成功に近づきます。 - 言語化能力が上がるので、何をやっても上手くいくようになる:
脳内を言語化できるようになるので、大学の勉強でも課外活動でも趣味の練習でも、何でも効率が上がります。 - 騙されなくなる:
それっぽいムチャなことを言っている人の話を聞いても論理が破綻していることに気づけるようになるので、騙されなくなります。
見て分かるように、メッチャ良いことだらけですよね。マジで人生が変わる、一生モノのスキルになります!
論理的な文章を書くにはこれさえ意識すればOK!
ここでいう「分かりやすい文章」とは、人の心を動かすストーリーや小説ではなく、何かを説明する文章のこと。例えば、このサイトで言えばビザの取得方法や大学のプログラムを紹介する記事などですね。
よく「分かりやすい文章を書くためには主語述語が~」などと言われますが、もっと大事なことがあります。
分かりやすい文章のカギは一文一文の美しさではなく、文章全体の論理的な構成にあります。
料理の例で言えば、美味しいカレーを作るためには「水道水を使うか高級ミネラルウォーターを使うか」が本質なのではなく、「いつ水を入れるか」が大事なのです。そういう細かい所は最終調整です。
そして具体的には、以下の2つを意識するだけでOK:
- 見出し構成をしっかり考える
- 各セクションをPREP法で書く
当たり前じゃね?と思った人もいるかもしれませんが、みんなこの基本的なことができていません。逆にこれができれば圧倒的に周囲と差別化できます。
本記事では、これらの具体的な説明をした後、その習得方法+文章を上手く魅せるテクニックについて解説します。
では早速、次のセクションで具体例を見てみましょう。

具体的な文章作成のコツ
1. 見出し構成を先に考える
見出し構成というのは、分かりやすく言ってしまえば目次の構成のことです。
要するに、各セクションの内容を決める前にまずは全体の構成をイメージしましょう、ということです。どの順番で情報を提示すると読者が理解しやすいかを考えましょう。
例えば、マレーシアの学生ビザの取得方法を説明する記事を書く場合、私だったら以下のような見出し構成にします:
- リード文
- 学生ビザ取得までの全体像の解説
- 具体的な学生ビザの取得手順
- 入国まで
- 入国~大学到着まで
- 入国後の学生ビザ取得の流れ(健康診断など)
- 注意点や補足、よくある質問
- 終わりに or まとめ
リード文や終わりにを入れるかは任せますが、中の構成がとにかく大事なのです。意識したポイントはこれ
- 全体像を提示して見通しを持たせ、そこから具体例に入っていく
- 具体例は読者目線で読みやすい順番に書く
結論ファースト
これはどこでも言われることだと思いますが、まずは結論ファースト。読者はまず全体像を把握すると安心して読み進められます。
今回のこの文章で言えば、先ほどの「論理的な文章を書くにはこれさえ意識すればOK!」というセクションがこれに当たります。何が大事なのかと、今後のこの記事の構成をここで書いているので、読者に全体像が伝わります。
話が下手な友達の会話を思い出してもらうといいんですが、オチがいつあるのか、今話している部分が全体で言うとどこら辺の立ち位置なのかが分からない人の話は長く感じて苦痛だった経験はありませんか?そういうことです。
読者視点で順番を考える
次に、その次のセクションの内容です。時系列と読者の視点を持ちましょう。
例えば、入国前の手続きが入国後の手続きの解説よりも後に書かれていたら変だし、読んでいて混乱しますよね?自分が読者だったらどういう順番でどの内容を知りたいかな?と考えれば、自然と論理的な順番になります。
具体的には、こちらはマークダウン記法(後述)をマスターすることによってこちらは自然と習得できます。
この記事で言う「論理的な文章を書くとなぜ良いのか?」セクション(先ほど書いたもの)は興味を持ってもらうためのHookです。こういうのはあってもなくても良いので、場合に応じて使い分けましょう。
あと、最後に補足やFAQセクションを入れて飾り付けをするのもオマケです。
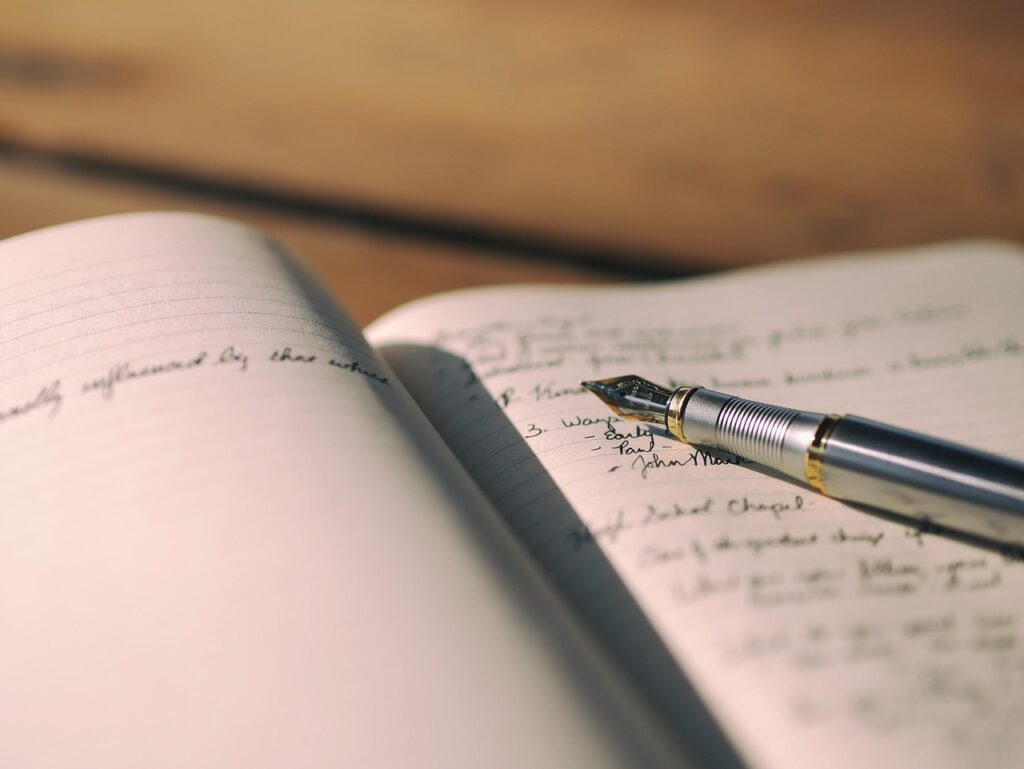
2. 各セクションをPREP法で書く
大まかな見出し構成を決めたら、各セクションをPREP法で書いていきましょう。
PREP法とは、以下の流れで書く手法です:
- Point(要点・結論):主張や結論を先に述べる。
- Reason(理由):なぜその結論に至ったのか、理由を説明。
- Example(具体例):理由を裏付ける事例やデータ、状況を提示。
- Point(要点・再主張):最後に結論を繰り返す。
学生ビザの取得方法はただやり方を解説するだけで説明がしづらいので、別の例を見ます。
ここでは、「みんな!毎週本を読もう!」という提案をしたいとします。すると、PREP法ではこう言えます。
- Point(要点):毎週1冊の本を読む習慣を持つべきです。
- Reason(理由):読書は知識を増やし、思考力や語彙力を向上させるからです。
- Example(具体例):私の先輩は毎週ビジネス書を1冊読み、仕事のプレゼンで使うアイデアや表現力が格段に向上しました。調査によると、読書を習慣にしている人は、そうでない人に比べて語彙力が○○%も多いそうです。
- Point(要点・再主張):毎週の読書は、知識とスキルを伸ばす簡単な方法です。
そうです。本当にただPREPに従って書くだけでいいんです。
これ、「そんなの1億回言われてることだし、既に知っとるわボケ!」と思う人もいるかもしれません。でも、みんな頭では分かっていると言う割に、できている日本人はほとんどいません。
当たり前のことだからこそ、これを自然に実践できるようになれば、抜きん出た文章が書けるようになります。
「お前の記事読んでみたけど、PREP法に従ってない構成のやつあるじゃねーか」と思った人もいるかもしれません。確かにその通りで、私の文章の中にはPREP法を崩しているものもあります。
が、基本をマスターすれば自分なりに型をアレンジしても分かりやすい文章が書けるようになります。なので、まずはPREP法をある程度マスターしましょう。
分かりやすい文章を書くための練習方法
以上のことを踏まえて私が考えた、分かりやすい文章を書くための方法はこれ:
- マークダウン記法をマスターし、PREP法を用いて何記事かブログ(note)を書いてみる
- 友達にフィードバックをもらう
- 👆の練習が終わったら、死ぬ気で1本何か大事な文章を書く
- 友達にフィードバックをもらいながら完成させる
以下のステップを順に実践することで、分かりやすい文章を書くスキルが身につきます。
👆もう既にここがこの練習方法のセクションの結論ファーストになっていることに気づきましたか(ウザっ)?
1. マークダウン記法をマスターし、PREP法でブログを書く
- マークダウンで階層構造をマスター:マークダウン記法を使うと、見出しやリストを活用して文章の構造を整理しやすくなります。論理的な階層を意識することで、全体の流れが明確になります。見出し(
#や##)や箇条書き(-や*)を使って構成を整える練習をしましょう。 - noteやブログで記事を書いてみる:マークダウンの構造を意識しながら、どこでもいいので文章を書いてみましょう。日記とかじゃなくて、何かモノや情報を人を説明する記事が望ましいです。その際にはPREP法を使って書くことを意識しましょう。
マークダウンって何ぞや?って人もいると思うので、そういう方は👇の記事を見てみてください。
マジで最初の「見出し構成を考えろ」っていうアドバイスはマークダウン記法をマスターすれば解決できます。
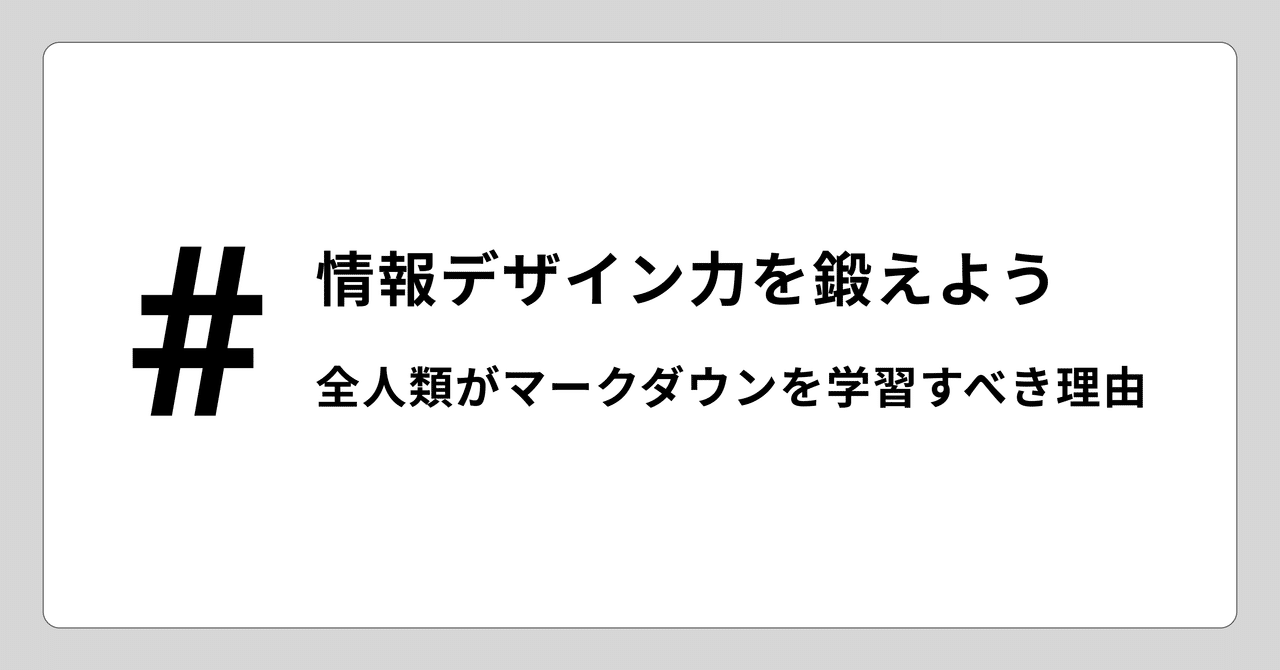
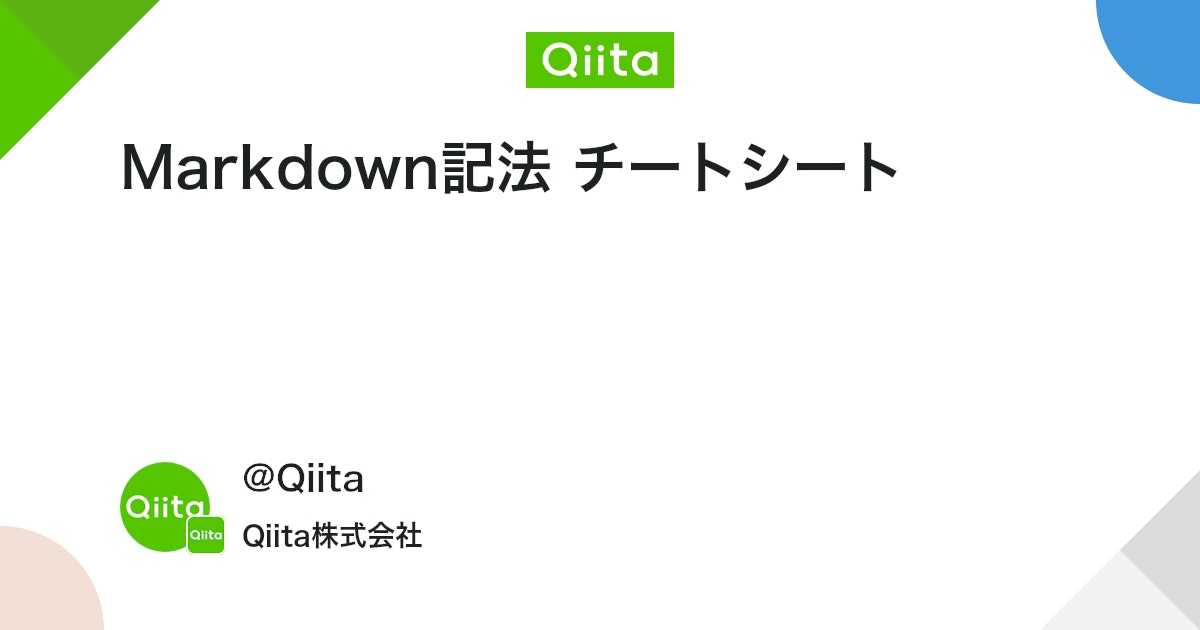
2. 友達にフィードバックをもらう
- 書いた記事を友達(上司でもなんでもいいけど)に見てもらい、厳しめのフィードバックを依頼しましょう。
- 特に、「どこが分かりにくいか」「論理が飛躍している部分はないか」を具体的に指摘してもらうと、改善点が見えてきます。
- 友達の視点は自分では気づけない弱点を教えてくれるので、積極的に取り入れましょう。

3. 死ぬ気で一本、重要な文章を書く
- 練習の集大成として、大学受験のエッセーやコンテストの応募文章など、実際に結果を左右する文章に挑戦します。
- この段階では、PREP法やマークダウンで鍛えた論理構成をフル活用。全体の見出し構成を先に作り、各セクションをPREP法で埋めていきます。
- 例:大学受験の志望理由書なら、「なぜこの大学か(Point)」「その理由(Reason)」「自分の経験(Example)」「再主張(Point)」の流れで書く。
4. 友達にフィードバックをもらいながら完成させる
- 重要な文章を書き上げたら、再度友達にチェックしてもらいましょう。
- フィードバックを受けながら、表現の曖昧さや論理の弱い部分を修正。複数回の見直しで、文章をブラッシュアップします。
- 特に、読み手が「ここでつまずいた」と感じる部分を重点的に改善しましょう。
こういう流れで、1と2のステップで練習を積み、それを生かして死ぬ気で大事な文章を書きましょう。1週間以上ウンウン悩むレベルで文章を推敲しましょう。
それを何回か繰り返せば、もう自然と普通の人よりも分かりやすい文章を書けるようになっているはずです。
ちなみに、ここからも分かるように量よりも質の練習がカギです。
たまに「私もブログ書きまくれば文章が上手くなりますか?」みたいなことを聞かれるんですが、多分なりません。
私の経験では、研究コンテストの論文や大学受験の志望理由書で「死ぬ気で」書いた数本が、文章力を飛躍的に伸ばしてくれました。ブログを始めたときと今でそう文章力は変わっていないはずです。
その力をそのまま転用すれば自然とプレゼンや面接も上手くなります。表現の細かい違いこそあるものの、基本的にはこの考え方を元にして文章を書けば英語のエッセーでも良いものが書けます。

文章を見やすくするテクニック
オマケとして、文章を「見やすく」するためのテクニックを紹介します。
ただし、あくまで小手先のテクニックなので、本質的に大事なのは👆であることを忘れずに。
音読する
正直これが一番効果あります。
文章を声に出して読み上げてみましょう。音読してみてつまずく部分や、歯切れが悪い部分は論理構成が弱いサインです。
一晩寝かせる&朝に文章を書く
書き終わったら一晩置いて読み直しましょう。ある程度時間を置いてから冷静な視点で読み直すと、誤りや不明瞭な部分に気づけます。
あと、文章は朝の気分がスッキリしているうちに書いた方がいいです。「夜中に書いたラブレターはキモい」なんて言われますが、まさにそういうことになりかねないので。
他人に見てもらう
第三者に見てもらうと、自分では気づけない問題点が見つかります。偉そうなことを書きましたが、私の文章も他の海外大生にフィードバックをもらうとボコボコにされることもありますし、逆も然りです。
一人だけでなく、なるべく多くの人に見てもらう方が良いでしょう。特に受験書類など重要な文章は、第三者にチェックしてもらうようにしましょう。
口調を統一する、表記ゆれを無くす
「です・ます調」もしくは「だ・である調」で書くのが基本です。一旦それで書き始めたら、最後までトーンは統一しましょう。
あと、表記ゆれを避けるようにしましょう。相手からの信頼を失います。基本的には個人の好みなのでどの表記でもいいんですが、一度使い始めたらそれを継続して使いましょう。
よくある例はこちら:
- 「おすすめ」「オススメ」「お勧め」
- 「など」「等」
- 「すべて」「全て」
- 「たとえば」「例えば」
- 「わかる」「分かる」
- 数字の全角(1)・半角(1)
あと、「一般的」みたいな一つの言葉として成立しているものに算用数字を使うのはやめましょう。「一般的」を「1般的」と表記している人とかいるんですが、「一郎」さんを「1郎」さんって表記すると違和感があるのと同じ理論でやめたほうがいいです。
といいつつ、この記事も雰囲気によって「良い(固め)」「いい(カジュアル)」とかバラけさせているので、表現のニュアンスを考えて使い分けられるのならOKだと思います。
一文60文字以上にはしない、改行・ブロックを意識
一般的には一文は40~60文字であると良いと言われているので、これ以上の長さにはしないようにしましょう。というか、スマホだと読みづらいのでサクッと短ければ短いほど分かりやすい気がします。
長くなる場合は、内容を省略するか、文章をそもそも分けるのがおすすめ。
改善前の例:
私はモナッシュ大学の学生をしていて、そこでコンピュータサイエンスを学んでいるんですけど、コンピュータサイエンス学部では主にプログラミングをしたりネットワークのセキュリティなどの多くの分野を勉強するんですけど、色々なことをやるので毎日課題が多くて大変なんですよね。
改善後の例
私はモナッシュ大学でコンピュータサイエンスを学んでいます。そこでは主にプログラミングやネットワークセキュリティなどを勉強しています。多岐にわたる分野を学んでいるため、課題が多くて大変です。
- 文章が長いので。内容ごとに3文に区切る
- 「コンピュータサイエンス学部」→「そこでは」として文字数削減
- 「多くの分野を勉強する」「色々なことをやる」といった同一内容は省く
あと、WordPress、note、はてなブログ、手書きなどなど、プラットフォームによって異なりますが、ある程度一文が長くなったら改行、もしくブロックを変えましょう。
個人的には、スマホで見たときに3~4行以上が一気にドカンと置かれているととても読みづらいなと感じます。個人的にはWordPressの場合はこういう基準でやると良いのではないかと思います。
- 意味は続いているが、長くて読みづらい時は改行(主に2~3行ごとに改行)
- 文章の意味や役目の切れ目として成立しそうであれば、積極的に改行(4行以上は1ブロックには置かない)
アイキャッチ画像やボケの文章を入れる
これはもう文章力じゃなくて、いかに飽きずに読んでもらえるかっていうブログで使える単なる裏ワザです。
👇みたいな画像をセクションの区切りに入れてみましょう。文章だけだと飽きられるので、視覚的に目立つものを入れて刺激を与え、離脱率を下げましょう。

あとは、お笑い的な意味で面白い文章を書く。
今回の記事は真面目なトーンで書きましたが、ふざけた文章を書いたりボケたり自虐したりしたほうが面白がって読んでもらえます。
そもそもの日本語力を上げる
一文一文の美しさは本質ではない!と言いましたが、日本語力も大事です。本とか新聞を読みましょう。
よく見落とされがちな例をいくつか挙げます。
頭痛が痛い、みたいな文章を無くす
同じような意味の言葉を無くしましょう。「頭痛が痛い」だと流石に分かりやすいんですが、
- 「以前、高校生の時に○○をしたことがあります」
- 「基本的には、毎日朝ごはんは大体食べるようにしています」
- 「私の個人的な意見としては、Aのほうがいいんじゃないかと思います」
こういう太字の部分みたいな感じで、意味的に同じ、もしくは省略してもいい言葉をたくさん並べている人が多いです。無駄なところは全部カットしてスッキリさせましょう。
といいつつ私の文章の中にもいくつかそういう箇所はありますし、これを自分で見抜くのは大変なので、ここは第三者に指摘してもらうほうが良いです。
文章のパーツ、階層構造を意識する
まずは文章のパーツごとの主体を明確にすること。実際の文章を用いて説明してみます。
改善前の例:
高校1年生の時、学校の先輩がアメリカの大学に進学し、その体験談を聞いたことが海外大学に行きたいと思ったきっかけです。
改善後の例:
高校1年生の時、アメリカの大学に進学した学校の先輩の体験談を聞いたことが海外大学に行きたいと思ったきっかけです。
太字の部分を変えてみました。
この文章の趣旨は、「体験談を聞いて海外大学に行きたいと思ったんだ」ということです。
「海外大学に行きたいと思ったきっかけ」がメインで、「体験談を聞いた」というのはそのトリガー、つまりオマケです。
あくまで「体験談を聞いた」ことがきっかけ(=大事なところ)なので、その前に情報をゴチャゴチャさせない。
「アメリカの大学に進学した」とかは「体験談」の補足、あくまでサブのサブに過ぎません(アメリカに行きたいという文脈なら別だが)。
「先輩の体験談」が主なので、「学校の先輩がアメリカの大学に進学し~」とか書くと、先輩が何をしたかが主役に見えてしまい、ゴチャります。
「○○した先輩の話」というパーツを意識しましょう。こういう感じで、なるべく主従関係をスッキリさせたほうが主語が明確で分かりやすい。
ここから、「真の趣旨を一番最初に持ってくる」というひと手間を加えてみましょう。
前回の改善案:
高校1年生の時、アメリカの大学に進学した学校の先輩の体験談を聞いたことが海外大学に行きたいと思ったきっかけです。
さらなる改善案:
海外大学に行きたいと思ったきっかけは、高校1年生の時にアメリカの大学に進学した学校の先輩の体験談を聞いたことです。
先ほどの太字の部分を変えるだけでもかなり読みやすくなったと思いますが、「海外大学に行きたいと思ったきっかけは~」という真の主張の部分を先に持ってくればさらにGoodです。何がメインなのかがこれでよりハッキリしました。
ね?文章の中のパーツを意識するだけで一文一文が生まれ変わります。これも言ってしまえば階層構造と言えなくもないですね。
接続詞・対等関係を意識する
接続詞の誤った使い方の例:
新しいスマホを買いました。そして、カメラの性能が良いです。
テストで100点を取ることを目指していました。でも、結果は100点でした。
こういう感じで、「そして(=順番の接続関係)」「でも(=対比関係)」など、接続詞の使い方がおかしい人もたまにいます。
前半の例では「カメラを買ったこと」と「カメラの性能が良いこと」を順序付きで説明する意味はないし、後半は「でも」とあるのに反対の内容が来ていません。
あとは同格の関係。
マレーシアのご飯は辛いです。また、宇宙の勉強にも興味があります。
これは極端な例なので分かりやすいと思うんですが、「また」とかそういうものを使って並列して並べる対象は同レベルや共通点があるものにしましょう。
修正ver.は書かなくても分かると思うので割愛しますが、みんな意外と変な接続詞の使い方をしていたりします。
あとは、「ので、ので、ので~」とか、「同様に、同様に」と何回も同じ言葉を繰り返してたりね。似たような言葉は使うにしてもリフレーズしないと単調な文章になります。これは英語だとより顕著になります(外国語だと語彙力が不足しているため)。
キリがないのでここら辺で終わりますが、基本的な日本語力を上げましょう。新聞とか本をたくさん読めばこの辺りは何とかなるでしょう。
終わりに
今回は分かりやすい文章を書くコツとその練習方法、文章を見やすくするテクニックについてご紹介しました。
分かりやすい文章を書くコツは、見出し構成を考えることとPREP法で書くこと。この2つをマスターすれば、誰でも論理的で伝わりやすい文章が書けます。
私自身、高校時代の論文や大学のエッセー、ライターとしての仕事を通じて、この手法が本当に効果的だと実感しています。
みなさんも文章で人生好転させましょう!



