ブログを見ている人はお気づきかもしれませんが、私は生きてるとついいろいろ考えてしまう性格の人なので、「日記まとめ」シリーズみたいな感じで考えたことを思想録として書いていくことにしました。
多分不定期で更新されますが、毎回思ったことを短めの段落で書く形式にしようと思います。あんまり有益性はないので、私の考えとかに興味がある人だけ読んでもらえればなと思います。
当たり前のことをわざわざ言う人って、何なんだろう
最近SNSを見ていて、「当たり前のことをわざわざ言う人」が気になることがあります。
例えば誰かが「マレーシアって〇〇な国なんだな」と投稿すると、「いや、実際に住んでみないと分からないよ。何も分かってないね」とかを返す人がいる。
もちろん、その言葉が間違っているわけではありません。
むしろ多くの場合、発信者を批判したいというより、「自分の経験も共有したい」とか「現実はもう少し複雑なんだよ」と教えたくなる気持ちなのかもしれません。
ですが、見ている側からすると少し水を差すように感じることがあります。せっかく誰かがその瞬間に感じたことを言葉にしているのに、発信の熱がすっと冷めてしまう感じがするんです。
みんな、旅行者の感想に過ぎないことなんて分かっていて、それを前提に楽しんでいるんです。ある程度のネットリテラシーがあるならば分かると思います。
もちろん誤情報を正すことは大事ですが、そういう感じだと共感や余白が消えてしまう気がします。
これはSNSに限らず、日常の会話にもよくあること。どれも正しいけれど、正論を言うことで温度が下がってしまう。
それよりも、ちょっとした感想をそのまま受け止める余裕がある社会の方が、SNSも会話も、もう少し心地よくなるんじゃないかと思いました。
肩書きで人を見てしまう自分
最近、自分が「肩書きで人を見てしまう」タイプの人間になりつつあることに気づきました。
昔から、人を見た目や印象で判断するのは良くないと思っていました。でも大学に入ってから、目に見える結果や実績がないとその人のことが信じられない自分がいることに気づいたんです。
例えば、何かの資格を持っている人や、コンテストで受賞している人、SNSで数字を出している人。そういう「分かりやすい(客観的な)結果」を持つ人を見ると、自然とすごいと思ってしまう。
逆に、実績のない人が良いことを言っていても、「結局コイツは口だけで何もしてないんじゃないか」と感じてしまう。その人が仮に水面化でメチャクチャ勉強していたり、起業の準備をしているかもしれないのに。
そういえば、高校生の頃、私自身の身を持って同じようなことを感じた経験があります。
努力している間は誰も見向きもしないのに、課外活動で全国優勝とかの結果が出た途端に「すごいね」と言われる。「結局、社会って結果しか見ないんだな」と思いました。
そして今、自分も同じ側に立っている気がして、少し悲しくなります。それが自分でも嫌なのに、社会全体が結果主義で動いている以上、そう思うのも自然なのかもしれません。
だって合理的に考えれば誰もが全員の努力を追えるわけではないし、結果で判断するのは仕方ないことです。
でも、肩書きや数字は努力の証であると同時に、見えない努力を覆い隠すフィルターでもある。人を実績だけで見てしまうのは、かつて自分が嫌っていた「浅い見方」そのものなんですよね。
最近、自分が何を言うかよりも誰が言うかを見ている自分がいて、ハッとしました。それは相手の問題ではなく、自分が肩書きという物差しでしか人を見られなくなっていたということ。
そう気づいたとき、少しだけ胸が痛みました。でも同時に、それを自覚できたこと自体が、きっと小さな成長なのだと思います。
SNSでの弱者アピールへの違和感
限界海外大生
最近、SNSで「弱者アピール」や「限界アピール」をする人が増えたように感じます。
例えば、「限界海外大生」とか「ADHDすぎて人生詰んだ」みたいなプロフィールや投稿です。
もちろん本当に苦しい人もいるし、それを発信することで救われる人もいるとは思います。でも、正直なところ、それをキャラ化しているような人たちを見ると少し違和感を覚えます。
だって例えば前者に関しては、友達と出かけたり、ジムに行ったり、SNSで発信できている時点で限界ではないと思うんです。本当に限界のときってスマホを開く気力すらないし、毎日徹夜しないと留年しちゃう!くらいの勢いじゃないとそもそも限界とは言わない(私的には)。
それなのに「限界〇〇」と名乗りながら楽しそうにSNSを更新している人を見ると、弱さを演出する文化になっている気がします。
こういう人はたくさんいるので特定の誰かについて言及しているわけではないんですが、強烈な違和感を感じます。まあ肩書きくらい好きに名乗らせろって感じではあるんですけどね。
頑張っていることを誇れるSNSがいい
最近は、「頑張っている自分」よりも「できない自分」「病んでいる自分」「不器用な自分」を出したほうが共感されやすいSNS構造になっています。
でもそれが行き過ぎると、「不幸であること」や「生きづらさ」そのものがブランド化してしまう気がします。
もちろん、何かを自慢すること自体は悪くありません。
見た目に自信がある人が自分の顔の写真を載せたり、筋トレを頑張っている人が体を見せたり、勉強ができる人が成績をシェアするのとかは、ある意味自然なことだと思います。
けれど最近はその反対で、「マイナスなこと」をあえて誇らしげに語る風潮が増えているように感じます。いわば逆マウントのようなものです。
弱さを語ること自体は悪くありません。でもそれが「自分の価値の中心」になってしまうと、本来の強さや前向きさが見えなくなる。
SNSの構造上、そうした共感は得やすいけれど、本当の意味での成長や希望を生むわけではないと思うんです。それに、そういう世界でポジティブな自慢を発見すると、斜に構えた視点でそれらを見てしまうことにもつながる。
だからこそ、もっと堂々とポジティブなことをもっと誇れる文化があってもいいと思います。
努力や成功を隠さずにシェアする。自分のできることや誇れることを語る。その方が、見ている人もずっと元気になれる。弱さを共有するよりも、強さを分かち合うSNSの方が、ずっと健全で明るいと思いました。

MBTIが流行った理由について
今の世代は未来が見えていない
最近、SNSでMBTI診断が流行っていますよね。16種類のタイプに分けて、自分がどんな人間なのかを分析するというあれです。
でも、なぜここまで広まったのでしょうか。私は、時代の不安と関係していると思っています。
コロナ禍で世界は一変し、先行きが読めなくなりました。その後、ChatGPTのようなAIが急速に進化し、将来の仕事や社会の形すら誰にも予測できなくなった。
つまり、今の若い世代は「自分がどんな未来を歩むのか」を想像できない時代に生きているんです。だからこそ、人は「自分が何者なのか」を知りたくなる。
そしてその答えを手っ取り早く与えてくれるのが、MBTIのような「ラベル(属性)」なのだと思います。
「自分はINTJだからこう」みたいな感じの言葉で自分を説明できると、人は少し安心する。先の見えない時代では、「正体不明な自分」ほど怖いものはないからです。
だから、たとえ16種類しかない単純な分類でも、そこにアイデンティティを感じられるのだと思います。
ラベル付けからの脱却
これはMBTIに限った話ではありません。例えば、「陽キャ」「陰キャ」「リア充」「非リア」、あるいは「お金持ち」「庶民」といった二元論的な分け方も同じ構造です。
本当は人間なんてグラデーションのように曖昧なのに、私たちはどこかで白か黒か、何かに属したいと感じている。
自分をラベルで定義することが、いまや「安心の手段」になっているんです。
もちろん、MBTIを楽しむこと自体は悪くありません。自分を知るきっかけにもなるし、会話のネタにもなる。
でもそれに過度に頼ってしまうと、ラベルの中でしか自分を見られなくなる危うさもあると思います。
本当の自分は16種類のどれかではなくてその間に広がる無数のグラデーションの中にいるし、別にそもそも何者でもなくたっていいのではないかと思います。
自分の中にある“老害の素質”
価値観の外側へ
最近、自分の中に“老害の素質”があるんじゃないかと思うことがあります。というのも、自分には柔軟性が欠けているなと思うことが度々あったからです。
例えば、先ほどのセクションで書いた「限界海外大生」の件。
よく考えたら、あれも「そんな名前つけなくていいだろ」と感じる時点で、もう相手の自由を狭めていたのかもしれません。「自分で好きに名乗らせろよ」と言われたら、確かにその通りなんですよね。
マレーシアの文化についても同じです。
予定を急に変えたり、時間にルーズだったりすることにどうしてもイラッとしてしまう。でもそれって、日本的な礼儀や自立を重んじる価値観で育った自分が、それを基準に他人を測っているだけなんですよね。
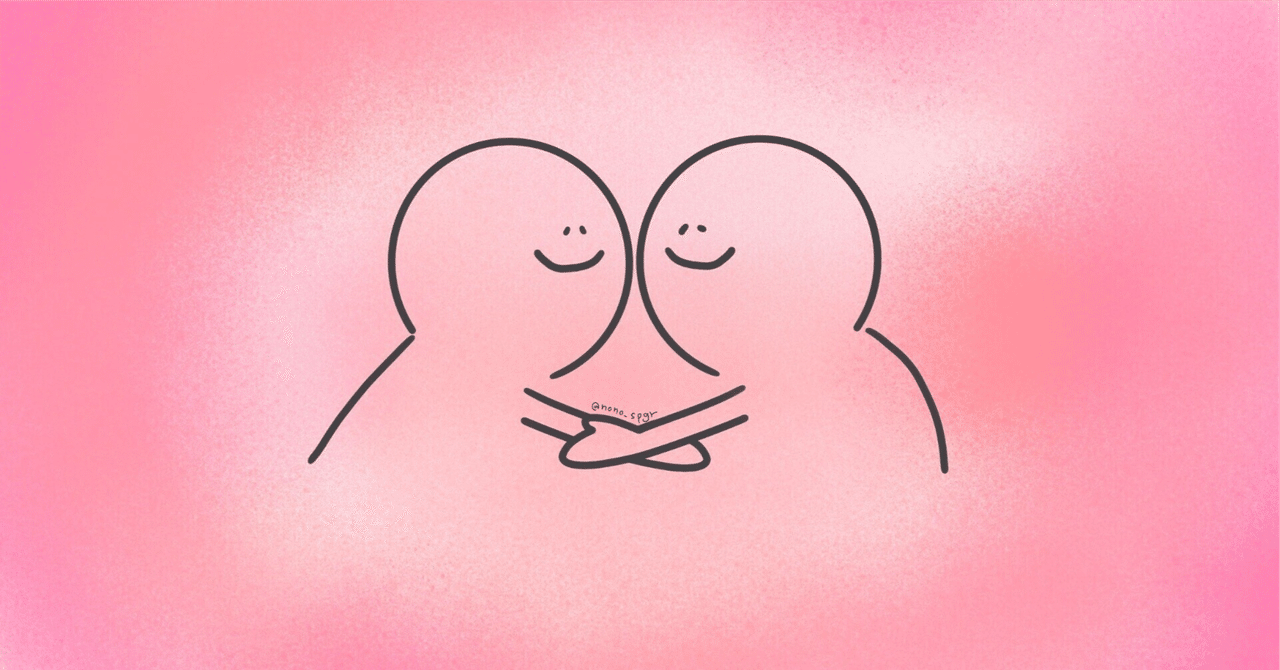
柔軟性を身に付けたい
つまり、「自分の常識から外れるもの」を受け入れづらい。そういう狭さが、自分の中に確かにあると思いました。
自分はこだわりは強いけど、でも論理的に考えるのが好きだし、言葉で人を説得するのも得意な方だと思います。
でも最近、それは必ずしも良いことではないと感じます。
ただ、社会に出て人と関わるほどに、正しさよりも柔軟さの方が大切だと感じるようになりました。
自分と違う考え方や生き方を受け入れること。それは妥協ではなく、世界を広げることなんですよね。
「自分が正しい」と思う気持ちは悪くないけれど、他人にもそれぞれの正しさがあるという視点を忘れたくないと思います。
気づけば、自分も年齢を重ね、少しずつ価値観が固まってきている。だからこそ、柔軟さを意識的に保ちたい。
もし自分の中に老害の素質があるとすれば、それを自覚できた今が変わるチャンスだと思っています。
終わりに
こういう感じで、これから自分の思ったことを思想録としてまとめていこうと思います。これに関しては結構書いてて楽しかったです。
もちろんツイートにしてもいいんですけど、ツイートで多分こういうものを求めている人は少ないと思うので、こっちにある程度まとめてちょっとしたエッセー位の長さで書いたほうがいいかもしれないなと思いました。
未来の自分がこれをどう思うかわかんないんですが、とりあえず思ったことを記録していくのは大事だと思うので、気が向いたらまた書こうと思います。


