時折、インターネット上でこのような男女の対立構造を孕んだやりとりが見られる。
- 男性:「女性は男性にモテると思って○○な化粧してそうだけど、正直男性側からしたら○○」
- 女性:「別にモテるためじゃなくて自分のために化粧してるんですけど」
それぞれ違った立場で生きているわけなので価値観の対立はある程度生まれても仕方がない気もするが、「異性のためではなく自分のための化粧」という主張を見た時にどこか腑に落ちない点があった。
そこで、今日はそれ(自己満足)についての自分なりの考えと、現代においてはWeb2が完全に浸透したことによって自己実現欲求と承認欲求の優先度が入れ替わり始めているのではないかという個人的な疑問について書いていこうと思う(この二つの話はそんなに関係ないですが)。

化粧は何のためにするもの?
化粧の定義
化粧の定義についてだが、大体どこを見ても「顔に紅やおしろいをつけて装い、自分および他人に美しく見せること」といったあたりで間違いないだろう。
いわゆる眉毛を書いたりリップを塗ったりするメイクがここでは分かりやすい例で、現状だと男性よりも女性のほうがこういった行為に割いている時間が多いのであろうことは容易に想像がつく。
定義を見れば「”自分及び“他人に美しく見せること」とあるため、自分のためにやっているという主張が正しいことになるが、ここでは言葉ありきの行為なのではなく、行為そのもののもつ意義から自己満足について考えてみようと思う。
化粧の起源
対象はさておき、基本的には「美しくなること」が化粧の目的であるわけだ。こちらのサイトによると、我々は「衣服を身に着ける前、3万年以上前から顔や体に色を塗る化粧をしていた」そうだ。
調べた限りでは、化粧をする理由としてはこのようなものがあるようだ。
- 魔除けなどのため:先ほどの例
- 成人した証:平安時代のお歯黒など
- 純粋な美しさのため:古代ローマ(?)あたりから存在していた模様
もちろん平安美人と現代の美人の定義が異なることからも分かるように、人々の中に根付く美の価値観は時代によって異なる。それどころか、マレーシアと日本ですらかなり価値観は異なるようだ(幼少期に見たテレビ番組のモデルなどの影響を受けているのではないかと個人的に考察している)。
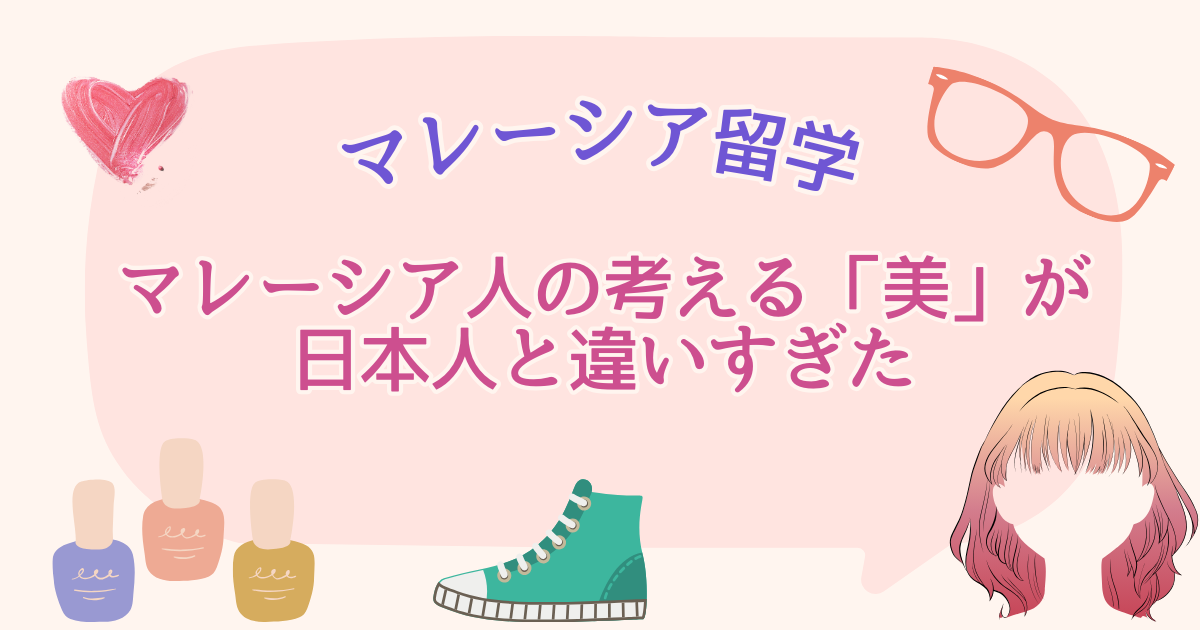
本能レベルでの自己満足
モテたい、という本能的な欲求について
ここから考えるに、どの時代にしろ、どの場所にしろ、人々が美を追い求めていくというのは変わらない普遍的なものであると言える。つまり、本能的に人間にインプットされた「何か」がそうさせているのである。
となると、私は個人的には美しさというのは「異性にモテるため」というのが根本的な起源なのではないかと思う。
例えば孔雀を思い出してみてほしい。孔雀はめちゃくちゃ派手で美しい羽の色をしているが、あれは一説によると「異性の気を引くため」であるという。
目立って天敵に襲われるリスクよりも、異性にモテて子孫を残せる可能性を上げたほうがメリットがあると判断したためこのような進化の系図を辿ったのだという。
これは現代の化粧にも言えて、わざわざ毎日ものすごい時間をかけてメイクをするというのは一見すると非合理的であるが、その分「自分が恥ずかしく思われたくない」「見た目を良く思われたい」といった気持ちのほうが大きいのだと考察できる(もちろん社会人になったらそれが「マナー」として求められる現代特有の風潮も原因ではあるが)。
我々は最近になってようやく秩序など獲得してきたとはいえ、あくまで動物の一種であるから、(特に古代から化粧の概念があったことを踏まえると)人間もこれに従って「異性にモテるため」に美を追求するというプログラムがDNA単位で刻まれていると考えないほうが不自然だと思う。
化粧はなぜ自己満足として機能するのか
自分では自己満足のためだとして、なぜ化粧をすることが自己満足になるのか考えてみたい。
自己満足というのは、「自分が何かやりたいこと、憧れていることを実現した際に得られる幸福感」だと言い換えることができるから、化粧をすることが何かしらポジティブな要素として認識されているのだろう。
では、なぜ化粧をすることがポジティブで自分にとって良いことなのだろうか?憧れの人の顔に寄せたい、もっと可愛く、カッコよくなりたい、など、理由は人それぞれであると思う。
ただ、根本的なレベルでなぜ美しくなると幸せを感じるのかと言えば、先ほどの例を鑑みると本能レベルでは全て「異性の気を引くため」という目的達成のためのDNAプログラムに基づいた行為に帰着されるから、それに喜びを感じるようになっているのではないかと私は思っている。
ここでなぜ私が冒頭で「異性のためではなく自分のための化粧」に疑問を呈したかという部分に話を戻す。
それは、仮に自分では自己満足、自己実現のためだと思っている行為でも、皮肉なことに深層心理レベルでは「他人(異性)のため」に行っている行為であるから、本人がどう思っているかという次元の問題ではないのではないか、と思ったからだ。
いい腕時計を付けたり服を買ったりすることでも同じことが言える。
ピアノと私の自己満足
ここで自分にも似たような例があったことを思い出した。
私はピアノが趣味で、今はYouTubeチャンネルもやるようになった。度々語っているが、なぜ私がピアノを始めたのかと言えば、まらしぃさんのピアノの弾いてみた動画を見て「カッコイイ!」と思ったからだ。
もちろんこのカッコイイは単純な憧れであり、「ピアノが弾ければモテるだろう」といった意味合いではない。よって、化粧についてもこれと同じ概念を適用すれば、確かに自己満足になるのかもしれないと思った。
だが、よくよく考えてみれば楽器演奏に関しても化粧と同じく「異性の気を引く」という目的をルーツに持っている気がしてきた。
こちらも古代から神をたたえたり何かお祝い事をする時に音楽を奏でるというのは起源の一つではあるものの、平安時代などに「管弦楽器ができる人は教養があり、素敵(モテる)」という風潮があったのも事実だからだ。
つまり、化粧と全く同じで自分自身は自分のためだと思っていても、根本的には素敵、可愛い、カッコイイといった憧れを孕んだ気持ちというのは、DNAのレベルで予めそうなるようにインプットされたものだったのである。
となると、純粋な自己満足とは何なんだろうと考えた時に、自分の中で定義ができなくなってきた。ボランティアで人を助けて嬉しい!となった経験はあるが(もちろん同性でも)、これ自体ももう何か遺伝子レベルでコントロールされた何かなのかもしれない。

マズローの欲求5段階説の転換点
自己満足に関連して、現代社会におけるマズローの欲求5段階説の位置づけについても少し思うことがあったので書いてみようと思う。
概説
知らない人もいるだろうから、まずはマズローの欲求5段階説について簡単に説明する。
マズローの欲求5段階説とは、アメリカの心理学者アブラハム・マズローが提唱した人間の欲求に関する理論で、人間は、5段階の欲求階層を満たすために行動すると考えられている。
- 生理的欲求:生き延びるために必要な欲求。具体的には、食、水、睡眠、排泄など。
- 安全欲求:安全に生活したいという欲求。具体的には、経済的な安定、健康、治安の良さなど。
- 所属と愛の欲求:社会に属したい、愛されたいという欲求。具体的には、家族、友人、恋人との関係など。
- 承認欲求:認められたい、尊敬されたいという欲求。具体的には、社会的成功、名誉、地位など。
- 自己実現欲求:自分の能力を最大限に発揮したいという欲求。具体的には、創造性、自己成長、自己超越など。
そしてこの数字が大きくなるほど高次の欲求とされ、基本的には数字の小さい部分から段階を追って達成されていくとされる。
例えば、人間は水や食料、睡眠の確保が出来ない状態で自己実現欲求(絵を上手に書きたい、スポーツでいいスコアを出したい)などを達成しようとはしないということだ。
Web2とSNSの発達による転換
近年になって「メタバース」なんて言葉を聞いたことがあるように、現代社会はWeb3.0の社会へ移行しようとしている最中だ。
Web○○とは何かというと、こちらのサイトの言葉を引用するとこんな感じになる。
- Web1.0:静的で、情報の流れが一方通行な Web の時代(新聞やテレビ)
- Web2.0:動的で、情報の流れが双方向な Web の時代(SNS)
- Web3.0:分散型インターネットの時代(ブロックチェーン、仮装通貨)
Web2.0というのは2000年代中頃以降に広まった概念とされる。先述のように今まさにWeb3.0へ移行しようとしている段階にあるわけだが、逆を言えばWeb2.0は概ね大衆社会に浸透しきったと言っても良い。
そして、YouTubeやInstagramを筆頭に、比較的幼い段階からSNSに触れて育ってきた「SNSネイティブ」なるものが登場し始める時代でもある。2004年生まれの私もその一部ではあるのかもしれない。
この世代の特徴としては、通貨などの従来の報酬よりも社会からの評価の方に重きを置き、こちらのほうがより高次のインセンティブとして機能する点にある。貨幣経済が評価経済になるということだ。
みんなが参入したがるYouTube Shortsがその例だが、こちらは広告報酬が従来の横長動画よりも低く大して稼げない代わりにバズりやすい、といった特性を有している。
インフルエンサーという言葉をよく聞くように、今はSNSのフォロワーが事実上の評価指標と化しており、それこそがステータスなのだ。こういった流れを見て育った世代の価値観もその影響を受けるであろうことは火を見るよりも明らかだ。
ここで何が言いたいのかと言うと、創造性、自己成長といった自己実現欲求(言わば自己満足?)よりも承認欲求のほうが高次の欲求として機能する日も近いのではないかということだ。
具体的に言えば、もともとは趣味でやっていたYouTubeチャンネルでも、視聴者のニーズに応えて数字を取るために方向転換したYouTuberなどがそれを体現していると言える。
時代がWeb3.0に移行する現代、こういった心理学的な転換点を目の当たりにして、すごい時代が来たなぁと思う。
当初の話題と無理やり関連付けてみれば、こういったSNS上での自分を見せ繕わなくてはいけないということ自体も、自分を美しく見せるという意味では広義の「化粧」に入るのかもしれない。



