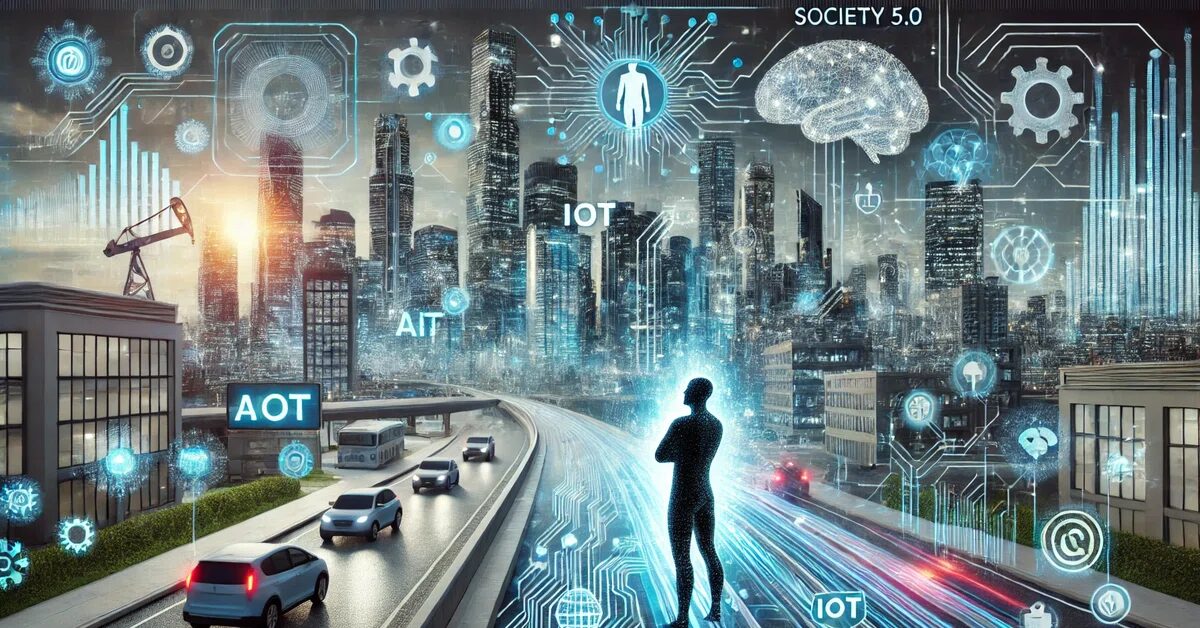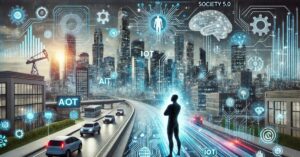テクノロジーが進化し、Society 5.0の時代が到来しつつある。この社会ではAIやIoT、ロボット技術が日常に溶け込み、人々の生活はより便利になると期待されている。
しかし、果たして本当にそれは「人間にとって快適な未来」なのだろうか?
Web2.0が浸透し、SNSで誰もが自由に情報を発信できる時代が訪れた。当初は画期的な進歩のように思えたが、やがてSNS疲れや誹謗中傷、些細なことでの企業の炎上といった新たな問題が顕在化した。
このように便利になるはずのツールが、逆に人々に精神的負荷をかける事態を招いている。
私は、これは人間の進化のスピードがデジタル技術の発展に追いついていないことに起因していると考える。
動物は数万年単位で進化し、環境に適応してきた。しかし、わずか数十年の間に私たちはガラケーからスマートフォンへ、さらには生成AIによる情報革命へと急激な変化を経験している。
そんな短期間で、人間の脳や体がこの変化についていけるはずがない。
Society 5.0の到来によって、暮らしが便利になるかと思いきや実は息苦しい社会になるのではないか。今回は、そんな話をしようと思う。
Society 5.0とは?
Society 5.0とは、日本政府が提唱する未来社会のビジョンである。
具体的には、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させることで、より豊かな社会を実現することを目指している。従来の情報社会(Society 4.0)をさらに進化させ、AIやIoTによる効率的なデータ活用を推進することが特徴だ。
例えば、自動運転車が普及すれば、交通事故が減少し、移動がよりスムーズになる。スマートシティが発展すれば、都市のインフラが最適化され、エネルギー消費が効率化される。医療分野でも、AIが診断をサポートすることで、病気の早期発見が可能になる。
ITの発達がもたらした悪影響
これまでの時代は、Web2.0によって表現される「相互の情報発信が誰でも可能になった時代」と言える。

地方在住でも情報に容易にアクセスできたりと、一見するとIT技術の発展による恩恵が多かったように思える。しかし、その一方で、
新たな社会問題も生まれた。
- バカッターの問題: 本来ならば当事者だけでのトラブルで済んだものが全世界で話題になることにより、それに悪影響を受けるものが出てくる恐れがある。
- 他者と比較する機会の増加: SNSの普及により、フォロワー数や「いいね」の数が新たな社会的ステータスとして機能するようになった。これにより、他者との比較が激化し、精神的なプレッシャーを感じる人が増加している。
- ネガティブな意見の拡散と企業の炎上: X(旧Twitter)などでは、少数のユーザーによる意図的な情報操作が可能になり、企業や個人が炎上しやすい環境が生まれた。
- ネットリンチの横行: かつては無視できたような問題も、インターネット上では膨れ上がり、多くの人々の攻撃対象となることがある。一度炎上すれば、修復不能なダメージを受けることも少なくない。
本来であれば些細なこととして流されるはずのものが、SNSの拡散力によって過剰に取り上げられ、無視できなくなってきているのが現代社会の大きな問題の一つだ。
また、別に昔の時代なら見過ごされていただろうとかそういうことが言いたいわけではないのだが、いちいち自分の発言がどう捉えられるのかを意識して生きなくてはいけない、などといった側面は、経済的な社会システム運営のための障壁ともなりうる。
見える世界が広がったように見えて、実は相互監視が強まったり、本来無視できるノイズを気にしながら生きなくてはいけなくなったとも言える。この流れがSociety 5.0によって加速する恐れがある。

デジタル化に人間は適応できるのか?
そして、こうした技術の進歩が人間の負担を軽減するとは限らない。むしろ、こういった社会に「適応しなければならない」プレッシャーが新たなストレスを生み出す可能性がある。
結論から言えば、私は人類が短期間でSociety 5.0に完全適応することは難しいと考えている。人間は短期間でそこまで変わることはできないからだ。
本来、人間を含む動物というものは数万年単位で進化し、環境に適応するものだった。
しかし、わずか数十年の間に私たちはフィーチャーフォン(ガラケー)からスマートフォンへ、さらには生成AIによる情報革命へと急激な変化を経験している。
動物の進化は割とのんびりしているのにも関わらず、IT技術の発展速度があまりにも指数関数的すぎるのだ。そんな短期間で、人間の脳や体がこの変化についていけるはずがない。
例えば、ペーパーレスなどと言ってデジタルノートを使って勉強する流れもあるが、手書きよりも記憶に定着しづらいと感じる人は多い。これは、紙に書くという行為が脳の記憶プロセスに重要な役割を果たしているからだ。
また、リモートワークの普及によって、対面でのコミュニケーションが減り、人間関係が希薄になったと感じる人も少なくない。デジタル空間でのやり取りは可能になったが、それが必ずしも「心地よい環境」になっているわけではない。
やはり、精神的にも肉体的にも、人間はそう短期間では変われないのではないだろうか。
未来の人間はデジタル環境に適応できるのか?
では、後の時代の人間はデジタル環境に適応することができるのだろうか?
可能性として、デジタル技術に適応した脳を持つ世代が生まれるかもしれないなとは思っている。そこまで短期間ではないにしろ、いずれ。
一遺伝子レベルでの適応には長い時間がかかるため、少なくとも数十年、数百年のスパンでは「デジタルに最適化された脳」を持つ人類が誕生するとは考えにくい。
むしろ、テクノロジーの進歩に伴う「デジタル適応障害」のような問題が今後増加するリスクすらある。
しかし、現在の子供たちは生まれた時からスマートフォンやタブレットに慣れ親しんでいる。私たちの親の世代から見たら考えられない光景だろう。
そのため、こういった経験が何かしら脳への影響を及ぼし、現在の私たちとは異なる情報処理の仕方をする子供が生まれる可能性もないとは言えない。
終わりに
Society 5.0の概念は、私たちに便利な未来を約束する。しかし、それは必ずしも「人間に優しい未来」ではないかもしれない。
デジタル技術が進化するほど、それに適応する負担が増え、私たちの心や体に新たなストレスをもたらす可能性がある。
また、人間の脳がデジタル環境に完全に適応する未来が本当に望ましいのか、という問題もある。自分自身の存在価値を見失う人が増えたり、デジタルデバイドが拡大する恐れがあるためだ。
便利になることと幸福になることは、必ずしも同義ではないのだ。
今後、技術が進歩し続ける中で、人間が本当に求める「快適な社会」とは何なのだろうか。
個人的には、「単にテクノロジーに適応するのではなく、人間らしさを守るためのバランスを模索し続けること」がそのためのヒントになるのではないかと思う。