高校生が参加できる課外活動の一つに、研究科学コンテストがあります。
自由研究的な感じで実験・調査したことをレポートにまとめ、応募するもののことです。国内大会の有名どころだと、「科学の芽」「日本学生科学賞」「JSEC」なんかがそうですね。
私自身も高校2年生の時に、全国規模のそこそこ大きなコンテストで全国最優秀賞をいただき、国際大会に出場した経験があります。
ですがこの研究科学コンテスト(以下、研究コンペ)、結構環境ゲーだったりして闇が深い課外活動だなと思っています。そのため、今回は研究コンペの良くないと思う点について踏み込んで書いてみようと思います。

個人的に思う、コンペの闇
まず闇ってなんだよって感じだと思うので、個人的に思うものを6つ挙げてみます。以下、詳細に解説します。
- 受賞者は結局は外部メンターの力を借りていることが多い
- 一つの大会の受賞者が他の大会にも複数応募し、賞を総なめしている
- SSH等でないと化学・生物系の実験がガチれない
- 審査員が自分の分野の専門家とも限らず、ジャッジが不公平
- レファレンスの書き方等の研究上の規則が甘く見られている
- 課外活動としての知名度が低い
最初の3つに関しては私はそれによって恩恵を受けていた側なのであまり強くは言えませんが、今後の発展を考えると良くないことなんじゃないかと思っています。
研究コンペの問題点
1. 受賞者は結局は外部メンターの力を借りていることが多い
上記のような規模の大きい研究科学コンテストの受賞者は、外部の指導者の力を借りている場合が多いです。例えば、実際に見たことのある例だと
- 親がその分野の専門家(研究職やその分野の企業で生計を立てている)
- 部活の教師がその道の専門知識をすごい持っている(or 院卒)
- 大学院生(or 院卒)のメンターに指導してもらっている
- GSC等で大学と共同研究を行っている
- その他教授や企業のエンジニアがバックについている
などが挙げられます。
私は音声工学の研究をしていたのですが、かく言う私自身も海外企業で働く現役エンジニア(博士号持ち)の方に指導してもらっていました。高校の先生の知り合いに偶然その方がいて、紹介してもらいました。
私の場合は大会の1週間前(書類は提出した後)からの出会いだったので質疑応答の練習をしてもらう程度でしたが、それでもかなりたくさんのフィードバックを貰えました。
ただ、SSH校などのコネがある環境が揃っていれば、計画立てなどの早い段階から外部の人間の力を借りることもできるでしょう。
ただ、こうなってくるとコンテストが高校生の実力というよりも大人の代理戦争みたいな感じになってきてしまうので、見ていてあまり気持ちよくありません。
実際にコンテストの後は、ネットでもたびたび「これ絶対高校生がやってないだろ」っていう研究とかが出てきて叩かれているのを見ます。
2. 一つの大会の受賞者が他の大会にも複数応募し、賞を総なめしている
科学の芽など以外にも高校生の研究コンペはたくさんあって(千葉大学の発表会など)、規則上複数のコンペへの応募もOKという場合も多いです。現状は学生科学賞とJSECが二重応募禁止になっているくらいです(しかもISEF側の事情だし)。
そして色んなコンペの受賞者リストを見てみると「この人他のコンペでも受賞してたよね!?」という例を良く見かけます。特に強力なGSCの研究成果を流用している人もいます。
これについては別に規則上は禁止されていないですし自分もその恩恵を受けてはいましたが、色んな高校生の受賞機会を奪っているという負の側面もあると思います。
そのため、もう少し高校生の研究コンペ(ある程度の規模以上のもの)の複数応募は禁止にした方がいい気もします。これが嬉しくてアカデミアの道を志す人もいると思うので、学生科学賞とかの受賞者が他のコンペも総なめとかしてしまうと未来の研究者の卵のモチベを潰してしまうことに繋がります。

3. SSH等でないと化学・生物系の実験がガチれない
これも環境面での格差になります。私の場合は田舎の一般高校でしたが、実験からまとめまでPC一台で完結する研究だったので問題ありませんでした。
しかし、生物や化学系の高度な実験を行いたいと思った場合、普通の高校だとできない場合も多いと思います。
それに対し、SSHの高校だったり資金がエグいほどある名門私立高校の場合、本当に高校?と思うようなレベルで実験設備が整っていることがあります。
気になった人はYouTubeでそこら辺の凄そうな設備紹介の動画などを見てみると分かると思います。やる気があっても設備面で研究を諦める、みたいなことがあったら悲しいですよね。
4. 審査員が自分の分野の専門家とも限らず、ジャッジが不公平
高校生の大会だと、物理分野、生物分野、みたいな感じで応募分野が大雑把に分類されていることも多いと思います。ただ、研究コンペの審査員と言っても、全分野の教授が揃っているわけではありません。
たまたま自分の研究分野と専門が被っている教授がいれば専門的なミスも指摘されてしまうでしょうし、逆にチンプンカンプンな教授からは研究の価値を理解してもらえないこともあるかもしれません。
私の研究していた音声工学は理系の中でもかなりマイナーな分野で、専門にしている教授も少ないです。そのため、研究発表の質疑応答の際に他の参加者は割と厳しめの質問をされていましたが、私の場合は誰でも答えられるような質問しか来ず、「何かすごいね~」みたいな雰囲気で終わりました。
こういう感じで、審査員がその分野の専門家でない場合はテキトーなこと言ってもバレなかったりしますし、それ以外でも割と発表の上手さや見せ方も関係します。現実問題仕方がない面もありますが、こういうコンテストは所詮コンテストなので、かなり運要素もあるということです。
研究系課外活動の実績としては、
- 高校生向けコンテストの受賞者
- 学会での受賞者
がいると思います。ただ、個人的には後者の方が圧倒的に凄いと思います。学会発表はその道の専門家がたくさんいるので、誤魔化しがコンペよりもできないからです。
5. レファレンスの書き方等の研究上の規則が甘く見られている
研究を行う上では引用を必ずします。そして、引用にはいくつかのフォーマット上の決まりがあります。
例えば、発言に対して「〇〇、△△(山田, 2019)」などとするAPAスタイルなどですね。
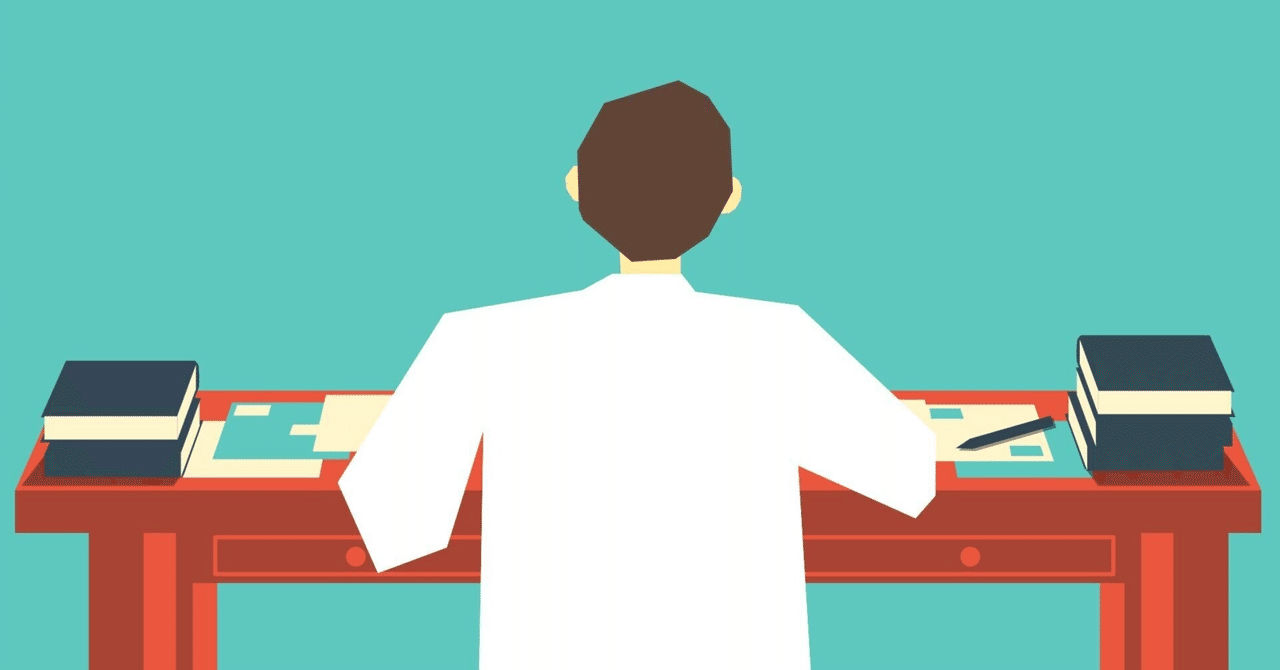
研究を行う以上、こういったフォーマットを守りつつCitationやReference Listをしっかり作るのは当たり前な気はしますが、ソースのタイトルとURLしか張り付けていない中高校生もかなり多いです。そうでなくても、書くべき情報を記載していなかったり、フォーマットに従っていなかったり。
もっと問題なのは、中高生レベルのコンペではたとえ引用文献がテキトーな書き方でも受賞できてしまうということです。受賞者の作品例なんかを見てみればわかります。
引用を適切に行わないと論文の盗用・剽窃などが疑われて問題になってしまいますので、内容以前に研究倫理としてこのあたりをもう少し厳しく審査してもらいたいです。
6. 課外活動としての知名度が低い
課外活動を頑張りました!と聞くと、やはり数学オリンピックや海外留学、ボランティアなどを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか?
個人的には、研究コンペを頑張っている高校生は大学で学びたい分野などもハッキリしていて、研究機関としての大学とは相性がいいんじゃないかと思っています。ですが、課外活動としての研究コンペは、まだまだ知名度が低いです。
逆を言えば参加者が少なくて入賞しやすいということなので気づいた人はラッキーかもしれませんが、そもそも知らなくてやる気すらなかった、という高校生もいるかと思います。
というより、総合的な学習の時間などはどの高校でも設定されていると思いますが、こういう活動はつまらない!といった印象を持っている学生が多すぎる気がします。教育を根本的に変えないと研究に興味を持つ人は増えないでしょう。
また、他国だと世界大会「ISEF」の出場者に対し、大学入試などで国が全面的にサポートを行ったりもしているそうです。日本でも推薦入試の要件として研究コンペが挙げられたりしていますが、もう少しこちらの受賞者(というより研究者そのものも)が優遇されてもいいんじゃないでしょうか。
終わりに
ということで、研究コンペのここ直したほうがいいんじゃない?と思う部分を書いてみました。
逆に私自身はこれらのことで恩恵を受けていた面も大きいのであまり強くは言えませんが、環境ゲー感があるのでもう少したくさんの高校生に門戸が開かれるといいなと思います。



