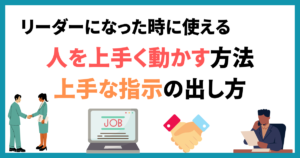学生のうちは、何かをやろうと気分的に盛り上がる瞬間が多いものです。
YouTubeを始めたり、noteを開設したり。最初の勢いは本当にすごい。けれど、数か月もしないうちに投稿が止まり、アカウントが放置されていることがほとんどです。マレーシアでもそういう光景を何度も見てきました。
これは「学生が気分で生きている」ことの象徴だと思います。やる気があるときに一気に動くけれど、少し飽きたり忙しくなったりすると、簡単に離れる。何かを継続する人の方が圧倒的に少ないのが現実です。
そして、そうした気分で動く人たちがチームを組むと、必ずどこかで崩れる。
なぜ学生のチームプレイは続かないのか。それは根性の問題ではなく、仕組みとして続かない構造になっているからだと思っています。
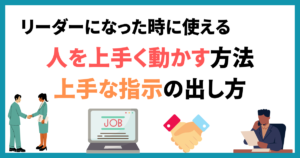
学生が継続できないのは「気分」で動いているから
学生が何かを続けるのが難しい一番の理由は、行動の軸が気分にあることだと思います。やる気があるときは一気に進めるけれど、少し疲れた瞬間に一気に離れる。
お金も契約も関係ないから、やめても誰も困らないし、本人にも大きな損はない。だから続ける理由もないんです。
自由であることは悪くないけれど、自由すぎる環境ではモチベーションの波に耐えられない。チームの中で温度差が生まれ、それが不満になり、最終的に崩壊します。
なので、「気分で生きる人たちの集まり」では、長期プロジェクトは成立しないというのが正直なところです。
実際、特定の課題のグループワーク程度ならともかく、学生チームで数か月以上の長期で課外活動をやる際に、チーム内部の温度感が原因で失敗に終わったケースをたくさん見てきました。
社会人チームが続くのは仕組みがあるから
一方で、社会人はやる気がなくてもやらなければいけません。仕事には契約と報酬があり、やらなければ生活に影響が出る。
だからこそ、多少気分が落ちても続けられる。継続できるのは精神力ではなく、仕組みがそうさせているだけなんです。
学生は完全に自由なので、そこが決定的に違います。つまり「自由」は気持ちいいけれど、「継続」という観点では致命的に弱い。
個人で続けてきた経験から思うこと
自分の場合、ブログを始めて2年ほどで750本近くの記事を書きました。たまに他のライターさんにお願いすることもありますが、基本的には95%以上は全て自分で手を動かしていると思います。
このスタイルにして良かったと今でも思っています。もしチームで運営していたら、きっと途中で温度差が出て喧嘩になっていたはずです。
実際、1年や2年のスパンで750本も書ける学生なんてそういません。自分のペースを保てるのは、自分しかいないと途中で悟りました。
もちろん、最初からチームを否定していたわけではありません。
でも学生同士のプロジェクトは、熱量の差がそのまま不和に変わる。だからこそ、最初から個人でやる方が結果的に早く、長く続けられると思っています。
学生チームを成功させるには構造が必要
もし学生のチームを成功させたいなら、「みんなで楽しくやろう」ではまず無理です。うまくいくのは、圧倒的なトップがいてトップダウンで動くチームか、誰かが抜けても他の人で補える構造を持っているチームだけ。
つまり、やる気が下がる人がいても全体が止まらない仕組みが必要なんです。学生同士の友情ベースで動くチームほど、気分の波で崩れる。
人の意志に頼るのではなく、仕組みで安定させることが大事です。
信用ではなく設計で動かす
最終的に言いたいのは、学生のチーム活動では他人を信用しすぎない方がいいということです。
「裏切られる」という意味ではなく、人は気分で変わる生き物だという前提で動くべき。信用ではなく、設計と役割分担でチームを回すこと。
もしそれが難しいなら、個人で動く方がいい。やる気が出たときに一気に進められるし、誰かに合わせてストレスを感じることもない。
学生のうちは、気分で生きていてもいいと思います。
でも、何かを本気で続けたいなら、気分ではなく仕組みで動く。それが、長く続ける人と途中で止まる人の一番大きな違いだと思います。