教育は、国が行う施策の中で一番重要なものだと思います。
教育が適切に機能しなければ、優れたリーダーが育たず、結果として国全体の競争力や国際社会での交渉力が低下してしまう可能性があります。
この前まで高校生だった現役大学生の私から言わせてもらうと、まだ日本の教育は改善のしようがあると思っています。今回は日本の教育の改善点について書いてみようと思います。
詰め込み教育は悪い方向に連鎖する
まず、現状の教育カリキュラムの問題点を考えてみると、一番は詰め込みベースの教育があるという点に問題があると考えます。
このような教育方法では、自ら考え、意見を持つ機会が不足し、受動的な学びが強調されてしまいます。そして、詰め込み教育には自分自身でしっかりと思考する能力が培えないという問題点があります。
何か自分で理由を考えたり意見を持ったりする機会が与えられないため、「周りがそうしているから」「社会はこういうものだから」と考えることが習慣化し、主体的な思考力が育ちにくくなってしまうのではないでしょうか。
実際、詰め込み教育が行われた結果、
- 小中高で知識中心の教育を受ける
- 長期休暇も含め、しっかりとした休息の機会が少ない
- 社会経験を積む機会が不足する
- 進路について考える十分な時間が確保されない
- 高校卒業時に進路を明確に決められない
- 深く考えずに志望校を選択する
- 進学後の大学生活が十分に充実しない
- 自分の適性やキャリアについて十分に考えないまま就職する
- 将来、自分の子どもにも同じような教育環境を提供する
- このサイクルが繰り返される
という悪循環が家庭でも起こっているのではないかと私は考えています。
要するに、与えられた知識を実際に社会で使ったり、自分の夢について真面目に考えるための自由時間がないため、何も考える暇なく新卒まで考える暇もなく一直線に送り出されてしまうわけです。教育の仕組みが変わらなければ、主体的な思考を持つ人材が育ちにくくなり、社会全体の進歩が妨げられる可能性があると言えます。
また、大学生が入学後に遊びに傾倒してしまう背景には、それまでの教育過程で自己表現や自由な選択の機会が不足していたことが影響しているのではないかと考えます。
自己決定の機会が少ないまま成長すると、自由を得た際にその反動が生じるのは自然なことなのかもしれません。
なぜ主体性を持たない学生が生まれてしまうのか?
社会システムが孕む問題
この問題は、学生個人の責任ではなく、社会全体の教育制度に要因があると考えます。受験が最終目標のようになってしまい、進路について考える機会が十分に提供されていない現状が問題の根本にあるのではないでしょうか。
例えば、高校生の段階では職業体験の機会が少なく、急に「志望校や学部を決めなさい」と言われても、自分の適性や興味を明確に判断するのは難しいでしょう。実際、多くの高校生が「周りが進学するから」と深く考えずに大学を選ぶ傾向があるように思います。
もちろん立派に志を持って進路選択ができている人もいますが、そんなのはごく少数です。
また、特定の職業を目指す場合でも、実際にその分野を体験したことがないまま決断しなければならないケースが多いのが現状です。例えば、医学部を志望する高校生が、実際の医療現場を見たことがないにも関わらず、想像とモチベーションだけで進路を決めてしまうこともあります。
こうした状況が続けば、「個々の適性に合った進路選択を支援する」というは十分に果たせないのではないでしょうか。
得た学びをどう社会に生かすのか
さらに、日本の高校教育は学力面では非常に高い水準にあるものの、その学びをどのように社会で活かすのか、また自身の進路選択にどう結びつけるのかを考える機会が少ない点が課題です。特に、進路選択と高校までの学びが十分にリンクしておらず、その橋渡しとなる機会が不足していることが問題だと感じます。
本来、大学は高度な研究機関であり、必ずしも全員が進学する必要はありません。しかし、実際には大学が「就職のための前段階」と見なされることが多く、一定の環境で育った学生は四年制大学に進むのが一般的な選択肢になっている現状があります。
日本では大学進学率に関する議論がなされることがありますが、重要なのは「どれだけの学生が主体的に学びたいという意欲を持って進学しているか」という点です。進学率の高さそのものではなく、進学の質や目的意識が問われるべきでしょう。
私は、日本の学生の(偏差値で計れるような類の)学力自体は他国と比較しても良いレベルに位置しているのではないかと考えています。マレーシアに来て感じましたが、日本は高校教育までで理系分野はものすごくレベルの高いことをしていますし、教育内容や受験のレベル感自体は誇るべきものはあると思います。
しかし、その得た知識や問題の解き方をどう社会に使っていくのか、自分の進路に役立てていくのかを教えてくれないという点が非常によろしくないと思っています。これも、何も考えずに新卒まで一直線に送り出されてしまう社会の構図に問題があると言えるでしょう。
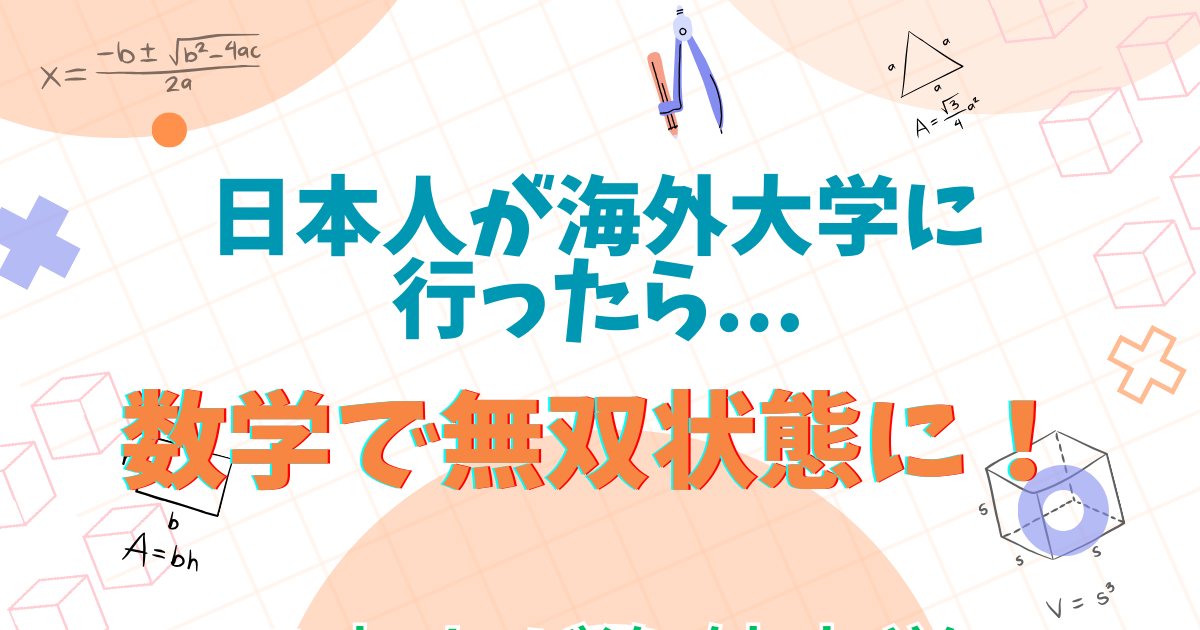
私の考える改善策
高大連携プロジェクトを増やそう
この問題を解決するためには、教育政策を通じて現在の仕組みを見直し、詰め込み教育の負のサイクルを断ち切る必要があります。
個人的には、以下のような取り組みが有効ではないかと考えます。
- 高大連携プロジェクト(例:GSC)の拡充
- 企業への補助金支給を通じた中高生向けインターンシップの活性化
- 進路をじっくり考えるための半年程度の長期休暇の導入
- 教育に情熱を持つ社会人を教育現場に呼び込むための施策
中高生のうちから社会や大学での学びを身近に感じられる機会を増やし、進路選択の精度を高めることが重要だと考えます。そうすれば、学生が主体的な意欲を持って進学を決定し、より充実した学びの場が提供されるようになるでしょう。
国全体で教育を変えるということ
新卒採用において、学歴を重視する企業が多いことが現状の教育の在り方に影響を与えているという意見もあります。
しかし、企業は営利組織であり、効率的な採用を行うために学歴を基準の一つとして用いている側面もあります。そのため、企業に直接変化を求めるのではなく、教育制度を見直し、主体的な思考力を持つ人材を育成することが長期的には社会全体の変革につながるのではないでしょうか。
教育が変われば、将来的にその教育を受けた人々が企業の意思決定層となり、結果として採用の仕組みや企業文化も変化していく可能性があります。
ただ、全学生に一定の性能を持つノートPCを配布する、国公立大学の学費を無償化するなどの施策も考えられますが、一度に大きな変革を行うのは現実的に難しいかもしれません。まずは実現可能な施策から段階的に導入し、その効果を検証しながら進めるのが現実的でしょう。
大学入試において、志望理由書や高校時代の活動報告書を必須とすることで、進学の意識を高める方法もあります。ただし、現在の教育環境の影響を受けた学生に対し、突然このような変化を求めるのは負担が大きいため、これについて段階的な導入が望ましいと考えます。
終わりに
日本の教育は、高校卒業後の進路選択の段階で主体的な意思決定が難しくなるような構造になっています。現状の詰め込み型教育がもたらす影響を考慮しつつ、社会と教育の連携を強化することで、より充実した学びの機会を作り出せるはずです。
教育の改革は、将来的に企業や社会全体の在り方にも影響を及ぼします。現在の学生が成長し、社会の中核を担う立場になった時、教育の在り方が変わっていれば、自然と企業の採用の仕組みや社会全体の価値観も変化していくでしょう。したがって、まずは教育政策から変革を進めることが必要だと考えます。
というわけで、私が高校生の時から日本の教育に対して思っていたことを書いてみました。


